プラスチック消費の削減には、包括的かつ踏み込んだ取り組みが不可欠だ。プラスチック汚染の削減を達成するためには、石油化学企業から消費者まで、すべての関係者が危機をコントロールすることが必要であり、断片的なアプローチではうまくいかないだろう。













近い将来、抜本的・包括的政策について国連で合意が形成されなければ、世界のプラスチック汚染は悪化の一途を辿る可能性が高い。そして “ピーク・プラスチック”を実現し、消費量を減少局面へ導くためには、国際プラスチック協定の交渉に携わる政府・石油化学メーカー・消費財メーカー・環境団体がより踏み込んだ対策を打ち出す必要がある。Economist Impactは日本財団の海洋環境保全イニシアティブ『Back to Blue』の下、同協定で検討されている政策の影響をモデル解析し、これら二つの結論を導き出した。
モデル解析に基づく予測には、無数の潜在シナリオが存在する。それゆえ有用な結果を導き出すためには、分析範囲を限定する作業が不可欠だ。今回の調査では、国際協定の交渉に関わる専門家の助言を受け、三つの政策シナリオに対象を絞った。これらはいずれも、世界全体のプラスチック・ライフサイクルを対象としており、プラスチック条約を協議する上でも、最もインパクトが高いと見込まれる政策だ。
複数の政策を並行して進めれば、プラスチック消費量の増加スピードを抑制させることは可能だ。しかしこれだけでは2050年までに消費量がピークを打って減少に転じることはない。世界のプラスチック汚染はそれほど深刻な状況にあるのだ。
国際協定の交渉担当者が新たな政策に関する合意形成に失敗した場合、G20諸国のプラスチック消費量は今世紀半ばまでに2倍以上増加する可能性が高い。














1
プラスチックの大部分(99%)は石油に由来している。プラスチック樹脂の大半は、北米と西ヨーロッパで生産されていおり、中国の生産量は3分の1を占めている。

2
プラスチック加工業者は、バージン材やリサイクル材を加工・組み合わせて、キャリーバッグから車の内装、歯ブラシから排水管ま で、さまざまなプラスチック製品を製造している。

3
小売業者と消費者は、製造された全プラスチックの半分以下 (45%) を包装に使用し、建築と建設は約19%を使用している。

4
プラスチック廃棄物のうち、リサイクルされたものは10%未満で、14%が焼却され、76%が埋立地や環境中に放出されている。大量のプラスチック廃棄物が輸出され、その大半は廃棄物管理能力の低い国々に送られている。


モデル解析の対象となった三つの政策シナリオが、2050年までに“ピーク・プラスチック”を実現することは難しい。これら三つを並行して進めたとしても、2019年時点のベースライン予測値である1.75倍から1.25倍へ伸びを抑制するにとどまり、消費量の深刻な増加には歯止めをかけることができない。
世界規模で使い捨てプラスチック禁止措置が実施されれば、拡大生産者責任[EPR]の義務化やプラスチック課税よりも大きな効果を発揮するだろう。2025年までに使い捨てプラスチック製品の1%がG20諸国で禁止対象となり、その後対象範囲が段階的に拡大すれば、2019年時点の1.48倍まで消費の伸びを抑えることができる
EPRは、包装材メーカーへ使用済みプラスチック収集・処理のコスト負担を求める仕組みだ。しかし同制度の導入による2050年までの消費の伸びは、2019年時点の1.66倍と、ベースライン予測(1.75倍)をわずかに下回るに過ぎない。対象企業の価格転嫁に伴う小売価格の上昇は、必ずしも大きな効果を生み出さないのだ。ただし廃棄物収集体制の改善やリサイクル率の向上など、プラスチックの環境流出抑制につながる可能性は高く、取り組みの一環として重要な役割を担うことは間違いない
環境税を導入すれば、プラスチック主要原料(バージン樹脂)のコスト上昇につながり、社会的負担が適正に反映されない価格構造の歪み是正や、再生原料の利用拡大が期待できる。しかしEconomist Impactのモデル解析によると、2050年時点の消費抑制効果は1.57倍で、2019年時点のベンチマーク値(1.73倍)との差はごくわずかだ。
234百万
トン
2000年
460百万
トン
2019年
765百万
トン
2040年
1230百万
トン
2060年
百万トン


エンパイア・ステート・ビル
百万トン


エンパイア・ステート・ビル
出典:OECD Global Plastics Outlook Database
2000年から2019年の間に、世界のプラスチック廃棄物発生量は1億5600万トンから3億5300万トンに増加し、126%の成長率となった。国連条約が各国政府のプラスチック廃棄物発生対策への献身的な行動に拍車をかけると仮定すると、この増加率は2040年までに74%まで鈍化すると思われる。
出典:OECD Global Plastics Outlook Database
156.2百万トン



欧州連合[EU]を除き、プラスチック・ライフサイクルに対する規制の多くは国・地方単位で行われている。しかしこうした国レベルの対策は断片的で、世界的な成果をもたらすには不十分である。
国・地域・地方レベルの規制の多くは、組織・個人による販売・使用を対象とするが、効果的施策のほとんどは義務化されていないのが現状だ。例えば、既に拡大生産者責任[EPR]制度が施行される国の多くでは、プラスチック包装材の大手ユーザー(特に日用消費財[FMCG]分野のメーカー・ブランド・小売企業)が参加企業の大部分を占め、小規模の国内企業はほとんど見られない。
過去には、リサイクル推進が最も効果的なプラスチック汚染対策と考えられていた時期もある。しかしOECDのデータを見る限り、現行の取り組みは大きな成果を上げておらず、循環経済への移行もほとんど進んでいない。また多くの国では、使い捨てプラスチック禁止措置の効果も限定的だ。こうした政策はあくまでも取り組みの一部であり、汚染緩和には追加的な施策が不可欠だろう。
14百万トン













2050年までに、プラスチック消費量は、いかなる政策介入もなかった場合、ほぼ2倍になると予想される(下表のベースライン系列を参照)。選択したすべての政策介入を行った場合でも、消費の伸びは鈍化すると予想されるが、それでも2019年の消費水準の少なくとも1.25倍にはなるとみられる。
使い捨てプラスチック製品の段階的な使用禁止(SUPP)
小売業者とブランドに課された強制的なEPR制度
バージン樹脂の生産に対するプラスチック税
各シナリオの適用には一定の前提があり、その結果、いくつかの課題が生じる。以下、各シナリオについて詳しく説明する。








禁止措置を実施済みのG20諸国で既に対象となっている製品の割合をベースライン値として使用。未実施の国については、国際プラスチック協定により2025年から禁止措置が義務化されると想定。開始段階で使用済みプラスチックの1%が禁止対象になると仮定して分析を行った(英国・米国を除く)。
G20諸国が禁止措置の対象割合を引き上げるペースが前年比10%ずつ拡大すると想定(例:2025の禁止措置対象が2%であった場合、2026年は10%増の2.2%)。
政策介入の影響を数値化するため、将来的な消費量を基準年である2019年時点の値と比較。上述の通り、政策介入が行われなかった場合の消費量は2050年時点で4億5100万トン(2019年のほぼ2倍)と想定している。禁止措置が0.5〜1%の製品を対象に開始され、段階的に20%程度まで拡大した場合(詳細については『主要な想定項目』を参照)、2050年時点の消費量はベースライン値よりも14%低い3億8500万トンにとどまるだろう。増加ペースは抑制されるものの、消費量は2019年の1.48倍まで拡大する見込みだ。
今世紀中頃までに増加ペースを著しく減速させるには、本シナリオの想定よりもさらに踏み込んだ方策が必要だ。現在対象外となっている有害製品へ重点的に取り組めば、社会的に有用なプラスチック製品(医療器具・食品衛生用品など)の過度な生産制限を伴わずに効果を実現できるだろう。例えば不法投棄・紛失・廃棄などの形で環境へ流出した漁網は、海洋生物が飲み込む、あるいは絡まるなどの形で深刻な被害を及ぼしている。
































企業ユーザー(つまり小売企業・消費財メーカー)には、製品の包装に使われたプラスチックの回収とリサイクル施設への輸送が、包装材メーカーには使用済み包装材の回収・分別と適正なリサイクル施設への輸送が義務づけられる。
企業による義務の遵守を徹底するため、政府はEPR規制を厳格に施行する(かなり踏み込んだ想定項目ではあるが重要な前提条件だ)。
使用済み包装材の回収・分別・輸送のために企業ユーザーが負担したコストは最終消費者に転嫁され、様々な商品の小売価格が上昇する。
国・プラスチックの種類ごとの価格弾力性を検証するため、このシナリオでは単変量回帰分析を用いた。価格弾力性は2000〜2020年の過去データをベースとしており、価格の変化が需要にもたらす影響を示している。最終消費者が負担する価格の上げ幅は平均2%と想定している。
EPRの義務化が世界全体で実現すれば、予測対象期間を通じたプラスチック消費量の伸びはベースライン値よりも減速する可能性が高い。実施後数年間(シナリオでは2025年の開始を想定)に見られる影響はごくわずかだが、その後は徐々に拡大する見込みだ。このシナリオでは、2050年までに消費量が2019年時点の1.66倍にあたる4億3400万トンに増加すると予測している(ベースライン予測では2019年時点の1.73倍)。
EPRの義務化がもたらす長期的影響は、使い捨てプラスチックの禁止措置やプラスチック課税よりも限定的だろう。想定される価格上昇率が現実化しても、今世紀半ばまでに追加的汚染をゼロにすることは難しく、政策効果という面で他の二つに見劣りするのだ。
ただし、これによってEPRの有効性が損なわれるわけではない。企業に収集・分別・リサイクルが容易な包装材の使用を促し、プラスチック製品のリサイクル性を向上させるからだ。
プラスチック汚染削減と循環経済の推進には、効果的なリサイクル体制の構築が不可欠だ。1980年代以降、政府・業界団体は積極的にリサイクルを支援してきたが、(上述のように)再生プラスチックの割合は全体の10分の1以下にとどまっている。その背景はいくつかあるが、特に大きな要因となっているのはコストの問題だ。
残りは焼却されるか、管理が行き届かないか、ポイ捨てされるかである。
出典: OECD Global Plastics Outlook Database
リサイクル
焼却処分
不適正処分
埋立処分


















様々なプラスチック製品の温室効果をCO2 1.7〜3.5kg相当、つまり化石原料由来のプラスチック1kgあたり1.7〜3.5kgのCO2が発生すると仮定している。
実効炭素価格は、排出権価格・炭素税・燃料税という三つの要素によって算出される。これらはいずれもカーボンフットプリントの高いエネルギーのコストを上昇させ、 低炭素の代替エネルギー活用を促進する施策だ。
エネルギー関連のCO2全体を対象とした最低価格のベンチマーク値で、炭素価格はこの値あるいはそれ以上に設定されることが多い。
このシナリオでは、炭素税率の引き上げがポリマーの価格動向によって相殺され、バージンプラスチック製品のコスト上昇につながると想定している。
効果的な炭素税制を実施すれば、消費量の伸びは今世紀半ばまでに減速する可能性が高い(ベースライン予測と比較した場合)。ただしその他二つのシナリオ(使い捨てプラスチック禁止措置・EPR義務化)と同様、消費量が横ばい状態あるいは減少に転じる可能性は低い。炭素税の実施により世界全体のプラスチック消費量は2050年までに4億900万トン、つまり2019年時点の1.57倍へ拡大。ベースライン値である1.73倍と比べれば、増加ペースは減速する見込みだ。
バリューチェーン川上への課税がG20諸国の消費傾向に及ぼす影響は、EPRの義務化よりも大きい。しかし使い捨てプラスチック禁止措置に比べれば効果は限られる。プラスチック・メーカーや消費者の行動変容を促すためには、追加的な課税措置が必要となるだろう。
プラスチック包装部品に1トンあたり200ポンド(247.42ドル)
使い捨て商品のプラスチック1キログラムあたり0.45ユーロ(0.49ドル)
レジ袋1枚につき3~5円(0.03~0.05ドル)の徴収を義務化
レジ袋1枚につき450-500ルピア(0.03ドル)の物品税、完全実施予定
多くの国が、プラスチックのライフサイクルのいずれかの段階において課税している。そのような税金の多くは、下流で課税されている。UNEPによると、2018年時点で27カ国がレジ袋の製造または輸入に税を導入しており、30カ国がレジ袋の使用に対して消費者に店頭手数料を課している。
スペインでは、プラスチック包装の製造業者と輸入業者、および量に応じた税(包装1kgあたり0.45ユーロ)が課されている。イタリアでも同様の税(税率は同じ)が2024年に施行される予定だ。
英国で2022年4月から施行されている類似の税は、再生プラスチックが品目全体のプラスチック含有量の30%を超えない包装材または完成品を対象としている点で上記の例と異なる。








本報告書では、三つの政策シナリオがもたらす影響をそれぞれ検証してきたが、現在策定中の国際プラスチック協定は複数の政策を同時に進めることが望ましい。
Economist Impactの分析結果によると、三つの政策を併行して進めれば、単体で政策を施行するよりも高い効果が期待できる。
ただしこのシナリオでも消費抑制効果は限定的だ。2050年までの消費量を3億2500万トン(つまり2019年時点の1.25倍)に抑制できるが、“ピーク・プラスチック”の実現は難しいだろう。
|
年 |
ベースライン |
S1 |
S2 |
S3 |
統合アプローチ |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.73
1.73 times 政策的介入を行わない場合の2019年の消費量レベルの
1.66
1.66 times EPRのみ実施した場合の2019年の消費量レベルの
1.57
1.57 times プラスチック生産への課税を実施した場合の2019年の消費水準の
1.48
1.48 times SUPPを禁止した場合の2019年消費量の
1.25
1.25 times 3つの政策手段をすべて実施した場合の1.25倍 基準値より低くても上昇
1.73
1.66
1.57
1.48
1.25
1.73 times 政策的介入を行わない場合の2019年の消費量レベルの
1.66 times EPRのみ実施した場合の2019年の消費量レベルの
1.57 times プラスチック生産への課税を実施した場合の2019年の消費水準の
1.48 times SUPPを禁止した場合の2019年消費量の
1.25 times 3つの政策手段をすべて実施した場合の1.25倍 基準値より低くても上昇
今世紀半ばまでにプラスチック消費量を下降局面へ移行させるためには、今回検証した政策シナリオよりも大胆な取り組みが求められる。例えば、使い捨てプラスチックの段階的禁止措置については対象範囲を大幅に拡大し、より厳格な目標を掲げるべきだろう。バリューチェーン川上におけるバージンプラスチック・メーカーへの課税についても、さらなる税率引き上げが必要だ。
Economist Impactのシナリオ分析によると、小売価格の上昇に伴って需要が縮小すれば、技術イノベーションの加速につながる可能性が高い。こうしたイノベーションは、プラスチック使用量の少ない、あるいは全く使わない代替包装材・製品の普及を後押しするはずだ。効果的なリサイクル体制の実現に向け、分別・リサイクル技術の進化も求められるだろう。
仮に主要ステークホルダーがこうした措置を受け入れても、一部のメーカー・小売企業・業界団体・消費者団体などから反対の声が上がること可能性は高い。現在交渉が進む国際プラスチック協定で、監視・実施体制の強化に取り組む必要があるのはそのためだ。
抜け穴の存在が、せっかく合意された目標を形骸化させてしまうことは、過去に示されてきた。例えば、EPR制度の実施時(特に低所得国)は、都市・地域レベルで監視体制を強化し、循環経済の構築に向けた税収の活用を徹底することが求められる。またプラスチック・メーカーやユーザー企業、小売企業の目標未達・規制逃れに対する罰金は、十分な抑止効果を持つ額に設定すべきだ。一部地域が規制の抜け穴となることを防ぐため、政策は可能な限り全国レベルで実施する必要がある。国全体を対象とすることが望ましいが、大国においては州・省レベルでも効力を発揮する可能性が高い。国・ステークホルダーによっては、国レベルの実施計画に基づきボトムアップの取り組みを進める、あるいは国際協定の枠内で明確な目標・義務を設定しないといったアプローチも有効だろう。
交渉破棄や効力不足などによって、協定が失敗に帰する可能性もある。しかし、現状打破に向けて多くのステークホルダーが前向きな姿勢を示し、協定実現のチャンスが過去にないほど高まっているのも事実だろう。








このデータ可視化ツールでは、上記のシナリオにおいて、より積極的な禁止/税率を選択することで消費のピークが達成されるかどうかを、モデル分析できる。各シナリオについて、最低税率、中間税率、最高税率の3つの仮定で出力をモデル化している。
最低税率は、条約によって各国が実施すべき必要最低限の努力を強制できることを想定。
中間税率は、各国がより高い禁止率と税率を選択するために積極的に努力することを想。
最大税率では、現在実行可能な最も積極的な禁止率と課税率を選択できる。
ユーザーは、各シナリオでどの程度の禁止・税率を希望するかを選択できる。シナリオの選択に基づいた新たなモデル分析が可能である。これらの結果は、データワークブックにダウンロードすることもできる。
ベースライン
シナリオ1
使い捨てプラスチック製品の段階的な禁止(SUPP)
シナリオ2
消費者に課される強制的なEPR制度政策
シナリオ3
バージン樹脂の生産にプラスチック税が課される
すべてのシナリオ
2022年3月、ナイロビの国連環境総会は、決議5/14 “End plastic pollution: towards an internationally legally binding instrument “を採択しました。この決議は、2024年までに国際的に法的拘束力のある協定を作ることを支持し、設計、生産、廃棄を含むプラスチックの完全なライフサイクルに焦点を当てるものです。条約交渉は2022年11月に始まり、プラスチック汚染に対処するために採用可能な政策オプションの範囲に関する議論が行われる見込みです。
現在進行中の条約交渉と並行して、Back to Blueイニシアチブの「ピークプラスチック」ワークストリームでは、選択した政策手段によってプラスチック消費曲線をどの程度曲げることができ、プラスチック汚染の軽減につながるかについての理解を形成するために、エビデンスに基づくアプローチを開発してきました。
将来のプラスチック汚染を防ぐために考えられる3つの政策オプションの有効性を検証するシナリオ分析アプローチを採用しています。採用した3つのシナリオは、プラスチックのライフサイクルを反映したアプローチです。全シナリオにおける重要な基本的前提は、これらの政策の遵守がすべての産業参加者に義務付けられることです。今回対象としたのは、世界のGDPの約78%を占めるG20の19カ国です。
テクニカルメソドロジーの全文は、メソドロジーノートをダウンロードしてご覧ください。

シナリオのオプションを変更することで、ピーク消費量がどのように変化するかを確認することができます。
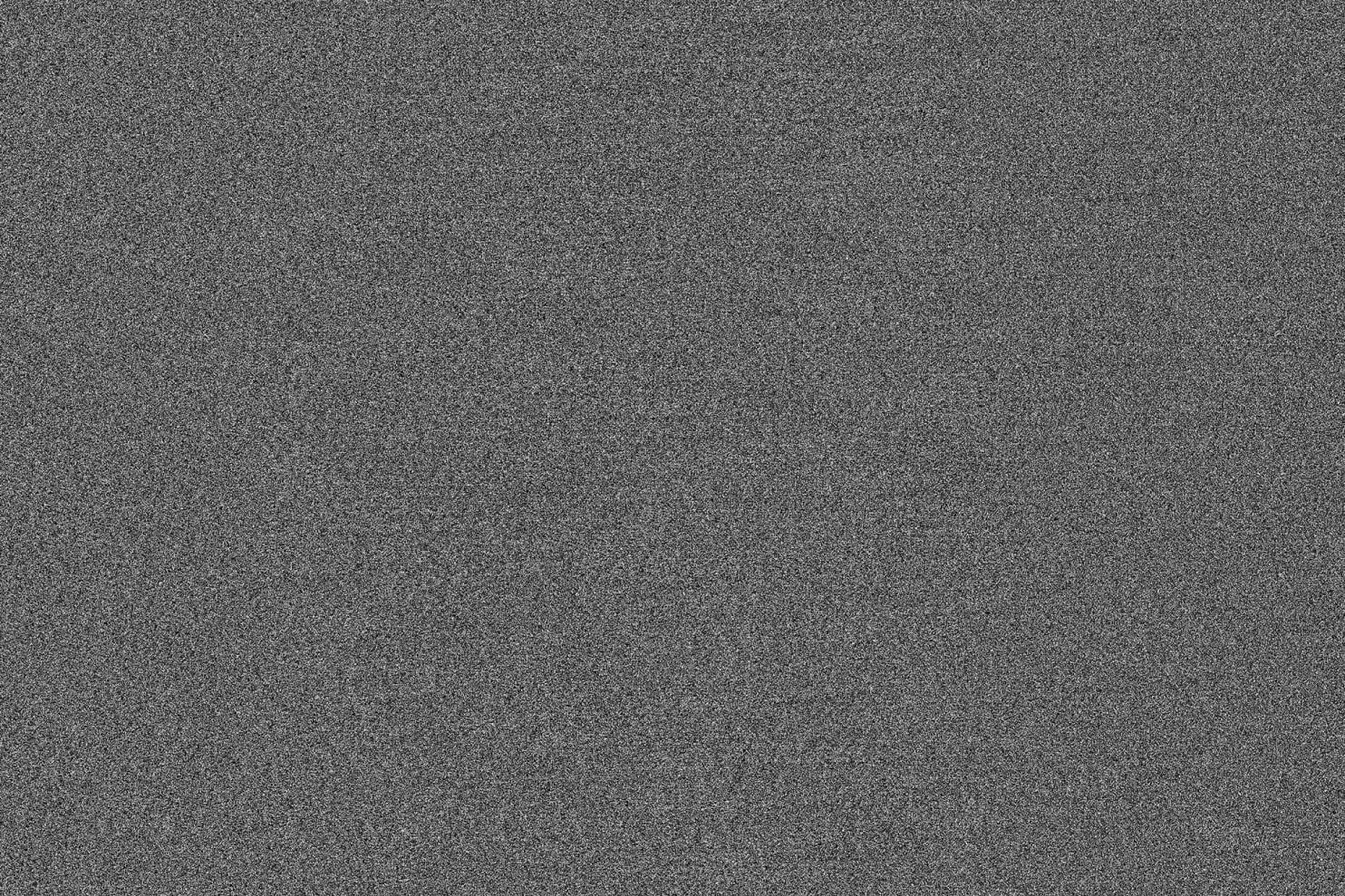
一連のポッドキャストでは、エコノミスト・インパクトのチャールズ・ゴッダードと近藤奈香が世界の第一人者に、海洋化学汚染の科学とその惨劇に対処する最善策について、話を伺います。
2030年の持続可能な開発目標の達成まで10年を切った今、グローバル・システムを検証し、人間の願望とそれを支える地球の能力とのバランスを取ることが改めて求められています。そこで、エコノミスト・インパクトは、洞察、イノベーション、影響力を組み合わせたコンテンツ・プラットフォームとコミュニティ・ハブとなる「サステナビリティ・プロジェクト」を立ち上げました。その目的は、真の変化をもたらす力を持つグローバルなステークホルダーを招集し、巻き込むことです。
エコノミスト・インパクトのワールド・オーシャン・イニシアティブは、健全で、活力ある経済力のある海洋を理想としています。年間を通じて、旗艦イベントであるワールド・オーシャン・サミットを開催し、海が直面する最大の課題についてグローバルな対話を促進し、持続可能な海洋経済を構築するための大胆な発想、新しいパートナーシップ、最も効果的な行動へと機運を高めます。
皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。編集やメディア関連のご要望があれば、メディアチームのメンバーが折り返しご連絡いたします。
Back to Blueにご興味をお持ちいただきありがとうございます。
Back to Blueのロードマップの共同設計をご希望の方、またはコンテンツ、イベント、記事、メディア関連へのご意見は、以下のフォームにご記入ください。ありがとうございました。

